ポーカーを学び始めると、「GTO(Game Theory Optimal)」と「エクスプロイト戦略」という言葉を頻繁に耳にするようになります。これらは一見対照的な戦略ですが、実は勝率を左右する重要な選択です。
GTOは理論上無敵とも言われ、一方でエクスプロイト戦略は相手の弱点を突く実践的な手法です。
「結局どっちが強いの?」「初心者はどちらを学ぶべき?」と悩む方も多いでしょう。
本記事では、初心者〜中級者向けにGTOとエクスプロイトの違いと使い分けについて、解説します。理論的な土台から実戦での応用まで順を追って説明しますので、読み進めるうちに理解が深まり、ご自身のプレイ成長にきっと役立つはずです。
GTOとは何か?ポーカー理論の土台をざっくり理解する

まずはGTOについてざっくり押さえましょう。GTOとは直訳すれば「ゲーム理論的に最適なプレイ」のこと。簡単に言うと、「相手に付け入る隙を与えない完全無欠の戦略」です。
もし人間が本当の意味でGTO戦略でプレイすれば、対戦相手はあなたの弱点を一切利用できません。相手にできるのはせいぜい引き分けに持ち込むことだけ…という理論上の強みがあります。
つまり、GTOは自分が損をせず長期的に負けない戦い方と言えるでしょう。
もっと具体的に言うと、GTO戦略では自分のプレイに偏りがなくなるよう工夫することです。特定のアクションやハンドに依存せず、ハンドレンジやベット頻度をバランス良く混ぜるのがポイントです。
例えば極端な例ですが、いつも同じようなタイミングでベットばかりしていると相手に読まれてしまいます。しかし、時にはチェックやコールも織り交ぜてバランスを取れば相手は簡単にパターンを掴めません。この「読まれないようにプレイを均等化する発想」の究極系がGTOなのです。
ジャンケンに例えると、自分が常にパーばかり出していれば相手はそれを察知してチョキで勝ち続けるでしょう。しかし、グー・チョキ・パーを全て同じ確率で出せば相手は手を読むことができません。
ポーカーでも同様で、特定のハンドでだけ必ずベットし他ではコールしかしない…といった癖があると鋭い相手には exploit(搾取)されてしまいます。そこで参加するハンドやアクションの頻度を均等にし、“どの場面でも弱点を晒さない”ようにするのがGTO戦略なのです。
要するに、プレイの癖を無くし、自分の行動を読まれにくくすることで相手に付け込む隙を与えない戦い方と言えます。 もっと専門的に言えば、GTO戦略では相手を無差別に想定したバランス重視のプレイを行います。
GTOの理論では、各アクションやハンドに適切な頻度が割り当てられ、ブラフとバリューの比率も数学的に調整されます。
例えば、リバーでポットサイズと同じ額のベットをしたとします。
このとき、相手は「同じ額をコールして、すでにあるポット+ベット=2倍のリターンを狙う」状況になるため、ポットオッズは2:1(勝率が33%あればコールできる)になります。
ここで、もしあなたが66%の確率でバリューベット(勝っているハンド)を出し、残りの33%でブラフをしていれば、相手は困ります。
なぜなら、
- コールすれば…66%で負け、33%で勝つ
- フォールドすれば…損はしないけど、33%の勝ちを逃す
つまり、コールしてもフォールドしても期待値が同じになるんです。
こうなると、相手には「どっちを選んでも得しない」という状態になります。これが、GTOでいう「バリューとブラフの比率を適切に混ぜる」という考え方です。
こうしたどちらを選んでも期待値0の状態を作るのがGTOの理想であり、これによって自分が一方的に損をすることを防ぎます。 とはいえ、完全無欠のGTOを人間が実践するのは事実上不可能です。実際、ノーリミットホールデムは未解明の複雑なゲームであり、現時点で完璧なGTO解は誰にも分かっていません。
スーパーコンピュータの力を借りたとしても、人間がリアルタイムでそれを再現するのは無理でしょう。ですから、「GTO戦略」と言っても実際にはGTO理論に基づいた”近似的な”戦略に過ぎません。それでも、GTO的思考を学ぶことには大きな価値があります。
バランスの取れたレンジ構築や、数理的に筋の通ったプレイを知ることは、ポーカー理論の土台としてプレイヤーの武器になるからです。実際のプレイで完璧なGTO行動を逐一とる必要はありませんが、GTOの「考え方」を理解しておくことは重要なのです。
プロの中には「あえてGTOなんて意識しない」という人もいます。しかし彼らでさえ、気づかないうちにGTOの考え方(=偏りのないプレイ)を自然と取り入れていることが多いです。
要するにGTOとは、ポーカーにおける守備力の最大化だと言えるでしょう。自分の戦略上の弱点を極力なくし、「相手が誰であってもある程度戦える」堅牢な土台を作る考え方がGTOの本質です。
次章では、この堅実なGTOに対し、あえて“最適”から外れてでも相手の弱点を突こうとするエクスプロイト戦略について見てみましょう。
エクスプロイト戦略とは?あえて“最適”を崩す理由

エクスプロイト戦略とは、一言でいえば「相手の戦略の歪みを見抜き、それを徹底的に利用する戦略」です。ポーカーでは多くのプレイヤーが何らかの癖や弱点を持っています。
エクスプロイトとは、そうした相手の弱点を見つけ出し、そこに付け込むプレイスタイルです。平たく言えば、「相手のミスに乗じて最大限の利益を狙う攻めの戦略」がエクスプロイトだと考えてください。
具体例で考えてみましょう。先ほどジャンケンで常にパーばかり出す人がいたら…という話をしました。この場合、あなたはひたすらチョキを出し続けるのが最適ですよね。それがエクスプロイト戦略の発想です。
ポーカーでも、例えばある相手が「大きなベットには絶対降りてしまう」タイプだと分かれば、その相手にはブラフを多めに仕掛けるのが得策でしょう。また別の相手が「あまり3ベットにコールしてこない」傾向なら、その人に対しては頻繁に3ベットを打って降ろし続ければ利益になります。
このように、相手ごとに効果的な攻略法をカスタマイズするのがエクスプロイトの醍醐味です。 エクスプロイト戦略を使う理由は明快で、その方がリターンが大きくなる可能性が高いからです。
GTOのように自分の戦略を守ることだけ考えていると、相手が大きなミスをしてくれてもこちらの得られる利益は限定的です。極端な例として、相手が毎回とんでもなく下手なプレイをしてくるのに、こちらが「理論的に最適だから」と無難なプレイばかりしていたら、本来もっと勝てるはずのお金を取り逃すでしょう。
そこで、あえてバランスを崩してでも相手のミスに付け込んだ方が得だと判断できる場面では、思い切って戦略を相手仕様に最適化する――これがエクスプロイト戦略です。
ただし、エクスプロイトにはトレードオフ(代償)もあります。一つは自分が逆に付け込まれるリスクです。自分が偏った攻め方をすれば、それに気づいた相手は逆手にとってこちらを反撃(カウンターエクスプロイト)できます。
「この人は私がチェックすると何でもブラフしてくる」とバレたら、相手はチェック/コールで全部受け止めに来るかもしれません。そうなると今度はこちらが不利になりますよね。エクスプロイトは相手との駆け引きなので、一方的にやり過ぎると相手も適応してくる点には注意が必要です。
もう一つのリスクは情報の不確かさです。エクスプロイトは相手の傾向や癖を前提に戦略を調整しますが、その読みが間違っていた場合大きな損失に繋がります。たとえば「この相手はブラフしないはずだ」と思い込んで大きなベットに全部フォールドしていたら、実は相手はしょっちゅうブラフしていて、降ろされ損だった…なんてことも起こり得ます。
誤った前提で調整してしまうとGTOから外れた分だけ損が大きくなるのがエクスプロイトの怖いところです。 要するに、エクスプロイト戦略はハイリスク・ハイリターンな攻めの戦術と言えます。
上手くハマればGTOスタイル以上に大勝ちできますが、見誤れば酷いしっぺ返しを食らう可能性もあります。そのため有効に使うには相手をよく観察しプレイの偏りを見つけることが重要です。オンラインならHUDなどの追跡ツールで相手の統計を見て判断できますし、ライブなら全てのハンドの様子に目を光らせて相手の癖を探る必要があります。
エクスプロイトは相手あっての戦略なので、「どんな傾向が見られるか」「それにどう対処すれば相手が嫌がるか」を考え続けることが求められます。裏を返せば、相手の数だけ攻略法があるため、GTO戦略にはない面白さや奥深さがあるとも言えますね。
なぜ初心者がGTOから入ると詰むのか
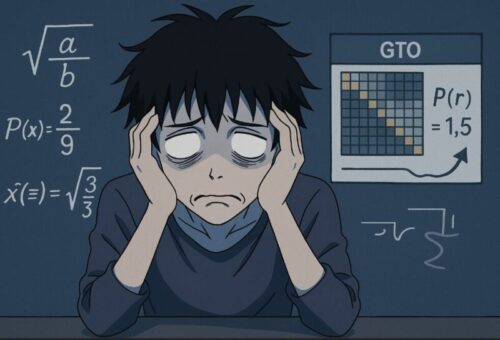
ここまでGTOとエクスプロイトを説明しましたが、「理論上最強のGTO戦略を最初から身につければ鬼に金棒では?」と思われたかもしれません。ところが実際には、初心者が最初からGTO一辺倒で学ぼうとすると壁にぶつかることが多いのです。その理由を解説します。
理由1: GTOは複雑すぎて消化不良になりやすい。
GTO戦略は数学や理論に裏打ちされた高度な戦略です。完璧に近いバランスを取るためには、ありとあらゆるハンドの組み合わせやアクションの頻度を頭に入れなければなりません。
例えばフロップのテクスチャごとに最適なベット頻度やサイズ、ブラフ比率…覚えることは膨大です。プロですらGTOを極めるのは難しいと言われるほどで、初心者が手を出せば「情報量が多すぎて訳が分からない!」となりがちです。
せっかくポーカーの勉強を始めても、GTO本やソルバー解析の難解さに挫折してしまっては元も子もありません。基礎体力がないうちに難しい理論ばかり先に身につけようとしても、土台が追いつかず崩れてしまうイメージです。
理由2: 初心者の戦う場ではGTOの前提が崩れている
BlackRain79という有名プロポーカープレイヤーは「マイクロステークス(低レート帯)でGTOを実践するのは悪手だ」と強く主張しています。彼によれば、GTO戦略が効果を発揮するのは「相手も高度な思考を持ち、バランスの取れたレンジで戦ってくる場合」です。
しかし実際、初心者が集まるような低レートの場では、大半の相手は理論的なレンジ構築などしておらずめちゃくちゃなプレイの方が多いです。
要するに、こちらがGTOを守っても相手がそもそもGTOに対応した戦い方をしてこないのです。その結果どうなるかというと、GTO戦略では相手の出方に関係なく堅実にしか勝てませんから、本来相手のミスから得られたはずの大きな利益を取り逃してしまうのです。
「全員がGTOを完璧に打てば誰も負けない(つまり誰も大きく勝てない)」とはよく言われる話ですが、これは裏を返せば「相手がめちゃくちゃなら、こちらもそれに合わせて相手のミスにしっかりつけ込んだ方が勝ちやすい」ということでもあります。
初心者卓ではまさに後者の状況が頻繁に起きるため、GTOに忠実すぎると稼ぎ損ねてしまうのです。
理由3: GTO至上主義は他の大事なスキル習得を妨げる
最初からGTOだけに集中してしまうと、相手から学ぶ姿勢が薄れがちです。ポーカー上達には「相手を観察し読む力」や「臨機応変な判断力」も重要ですが、GTO戦略は基本的に自分のゲームプランを崩さないことに重きを置きます。そのため、初心者がGTOに固執するあまり「相手が何を考えているかより、自分の取るべき理論行動ばかり考えてしまう」事態になりかねません。
これでは相手の癖に気付く練習や、状況に応じた柔軟なプレイの経験が積みにくいですよね。実戦ではイレギュラーな出来事が山ほど起こるのに、理論通りの対応しか知らなければ対処できずオロオロしてしまうかもしれません。
以上のような理由から、初心者がいきなりGTOだけで戦おうとするのは非効率的だと言えます。
実際、ある日本のポーカー情報サイトでも「初心者にとって一番良い戦略はエクスプロイトを徹底すること」と明言されています。まずは相手のミスを確実に拾って勝率を上げることが肝心で、難解なGTO理論の追求は二の次でも問題ないです。
もちろん、「だからGTOなんて学ぶ必要ない!」という極論ではありません。GTO理論を学ぶこと自体は長期的に見れば有益です。ただ、タイミングと配分が大事です。
ポーカー歴が浅いうちは、GTO理論は基礎知識としてほどほどに押さえつつ、それ以上に実戦的な読みとエクスプロイトを優先した方が成果を実感しやすいでしょう。まずは相手に応じた柔軟な戦い方で勝ち癖をつけ、徐々に高度な理論にも取り組んでいけば良いのです。
次章では、実際に勝っている中上級プレイヤーたちがこのGTOとエクスプロイトをどう使い分けているのか見てみましょう。
勝ち組プレイヤーはどう使い分けているのか?

トッププレイヤーや勝ち組と言われる人たちは、GTOとエクスプロイトを状況に応じて使い分けています。彼らは決してどちらか一方に偏っているわけではなく、まるでスイッチを切り替えるように戦略のギアを変更しているのです。
具体的にその実例や理由を見ていきましょう。 分かりやすい例として、海外の超高額ノーリミットゲームに参加しているプロ達の戦略があります。ある記事によると、彼らが戦うテーブルには大富豪のアマチュア(いわゆるフィッシュ)が約7割、残りの3割がプロという構成だそうです。
このような場でプロたちは、お互いプロ同士で対戦するときは極力GTOに沿ったプレイをし、一方で資金力はあるが腕前は劣るアマチュアと対戦するときにはGTOから離れてエクスプロイト重視のプレイに切り替えています。
つまり、強敵には守備重視、弱い相手には攻撃重視と相手に合わせて戦略を変えているわけです。プロ同士ではお互い隙が少ないため下手に崩すとやられるのでGTOで自分の身を守りつつ、フィッシュ相手には存分に弱点を突いて稼ぎにいく――この柔軟さこそ勝ち組プレイヤーの最強戦略です。
また別の視点では、「まずGTOを基本戦略として身につけ、その上で状況次第でエクスプロイトする」というスタンスのプレイヤーもいます。Upswing Pokerの記事では「GTOベースの戦略は完璧なデフォルトプランになる」と述べられています。どんな相手にもある程度有効で、かつ自分が大怪我しない戦略としてGTOを基本に据えておき、そこから先は相手の特徴に応じて微調整(=エクスプロイト)していくという考え方です。
実際、ポーカートーナメントなどで安定して勝つプロほど、「まずは相手に関係なく自分のゲームプラン(GTOベース)を持ち、それから相手の癖を見て調整する」と言っています。
特に最近はソルバー研究が進み、トッププレイヤーの多くはGTO理論をしっかり勉強しています。試合では、GTO理論で培った土台をベースにしながら、勝負所では相手の隙を見逃さず、柔軟に攻めていくというわけです。
興味深いのは、必ずしも全員がGTO寄りからスタートするわけでもない点です。プレイヤーのタイプによっては「最初はエクスプロイト型で、相手がそれに順応してきたら徐々にGTOバランスを意識する」というアプローチの人もいます。
例えばライブゲームで相手の反応を読むのが得意な直感派のプロは、序盤から積極的に相手の癖を探ってエクスプロイトし、中盤以降相手が対応してきたら一旦レンジを引き締めてGTO寄りに戻す…なんて芸当もします。
要は、勝ち組は一方向ではなく双方向に戦略を行き来できるのです。 このように聞くと難しく感じるかもしれませんが、要するに勝っているプレイヤーほど「両方の戦略の利点と欠点を理解した上で、その場に合った選択をしている」ということです。
彼らはGTOとエクスプロイトを対立する概念とは捉えていません。むしろ「GTOとエクスプロイトは同じコインの裏表」のような関係で、状況に応じて裏表を使い分けて初めて一枚のコイン(=トータルな戦略)が完成すると考えているのです。だからこそトップ層では「片方のスタイルだけを極めても一流にはなれない。両方理解してこそ本物」という声も多いんですね。
場面別:GTOとエクスプロイト、どちらを使うべき?

では具体的に、どのような場面でGTO寄りに戦い、どのような場面でエクスプロイトを仕掛けるのが良いのでしょうか。ここではいくつかのシチュエーション別に、戦略の目安を整理してみます。
相手が未知数・強そうな場合(特に初対戦や卓内に強者が多い状況)
基本はGTO寄りで臨みましょう。相手の傾向がまだ掴めていない時や、明らかに実力者相手には下手に隙を見せると危険です。まずは自分のレンジを崩さずバランス重視で戦い、こちらの弱点を突かれないようにします。
GTOベースのプレイは誰にでも通用する安全策であり、相手が強いほど有効です。
相手が明らかに弱い場合(経験が浅い、ミスが多いプレイヤー)
積極的にエクスプロイトしましょう。相手のプレイに極端な偏りやミスが見られるなら、こちらもそれに合わせて戦略を調整した方が断然お得です。
たとえば「この人はほとんど降りない」と分かればバリューベット中心に、「この人はちょっとのリレイズですぐ降りる」と分かればブラフ多めに…といった具合です。
特に初心者卓では「基本はエクスプロイト」で問題ありません。 ただし、同じ攻め方を続けすぎると、相手も徐々に対応してくる可能性があります。 相手の反応をよく観察しながら、必要に応じて戦い方を調整する柔軟さも持っておくと安心です。
自分が情報を十分持っている場合(相手の統計や過去のプレイ履歴が豊富)
この場合もエクスプロイトを検討します。オンラインでHUDのデータが蓄積していたり、長時間同卓して相手の癖を掴んだりしているなら、それを活かさない手はありません。
具体的な数字(VPIPやPFR、フォールド率など)が物語る相手の穴に対してピンポイントに攻めましょう。
逆に情報が乏しければ無理な読みは禁物で、その際はやはりGTOバランス重視に戻す方が安全です。
自分がマルチテーブル中または疲れている場合
こうした状況ではGTOベースのプレイが役立ちます。たくさんのテーブルを同時にこなすときや長時間プレイで頭が回らなくなってきたとき、いちいち相手ごとに細かな調整をするのは難しいですよね。
GTO戦略をデフォルト戦術として体に染み込ませておけば、多少自動操縦気味でも大崩れしませんし、安定したプレイができます。事実、オンラインでマルチテーブルをプレイする勝ち組は「GTO通りに打って、明らかなフィッシュにだけ注意を払う」という人が多いです。
集中力が落ちる局面では、自分のプレイを守ってくれるGTO思考に立ち返るのも得策です。
ゲーム形式やステージによる違い
一般にキャッシュゲームは同じメンツと長く打つことが多いので、後半になるほど相手の癖が分かってきます。そのため徐々にエクスプロイト比率を上げるイメージです。
一方トーナメントではテーブル移動もあり相手が入れ替わるため、読みに頼りすぎずGTO寄りの安定策が重要になる場面もあります。ただし、終盤のバブルや賞金の階段(ICMが絡む局面)では、「誰が慎重で誰が飛び込み覚悟か」を読んでエクスプロイトしたりと、読みの重要度が上がる局面もあります。
つまりゲーム形式や局面によってもGTO/エクスプロイトの配分は変化します。状況ごとのセオリーはありますが、最終的には「今この瞬間はどちらが適切か?」を自分で判断できる柔軟性が求められます。
以上をまとめると、「基本はGTOの考え方をベースにしつつ、状況に応じてエクスプロイトに切り替える」という流れになります。そして経験を積むほど、「このタイプの相手には早めに攻めよう」「この相手は様子見で慎重に」といった勘どころが養われていき、切り替えの判断も洗練されていくでしょう。
結局どちらが稼げるのか?

ここまで読んで、「で、結局どっちの方が儲かるの?」と感じている方もいるかもしれません。正直なところ、この問いに対する明確な正解は「状況による」としか言えません。
GTOとエクスプロイトはそれぞれ性質が異なり、一長一短があるからです。
一般に言われるのは「エクスプロイトの方が利益が出やすい」ということです。相手の弱点さえ見つけてしまえば徹底的に攻撃できるので、理論通りのGTOプレイよりも大きなリターンを得られる可能性が高いからです。
特に技術差がある場面では、GTOでは相手のミスから最大値を回収できませんが、エクスプロイトなら相手が気づくまでずっと搾取し続けられます。実際、先に述べたように初心者の多い低レートでは「エクスプロイト徹底が最も勝てる」とまで言われています。
しかし「常にエクスプロイトが稼げる」と決めつけるのはまだ早いです。なぜならエクスプロイトはリスクと隣り合わせだからです。確かに弱い相手には爆発的に勝てるかもしれませんが、相手がこちらの意図に気づいた途端に形勢が逆転したり、読み違いで大火傷したりする可能性もあります。
一方GTO戦略は、爆発力こそありませんが相手に関係なく安定した成績を出せる強みがあります。極端な話、卓上の全員がGTOプレイヤー同士であれば互いに大きなミスは犯さないので、勝ち負けは紙一重になります(その代わり誰も大負けしにくい)。
つまり、エクスプロイトはハイリスク・ハイリターン、GTOはローリスク・ローリターンとも言えるでしょう。この2つはトレードオフの関係にあり、「どちらが稼げるか」はテーブル上の相手や自分のスキル次第で変わってくるのです。
環境別に考えてみましょう。相手がミスをしてくれるようなテーブルでは、こちらは無理にバランスを取る必要はありません。強い手ではしっかりベットし、弱点を突いて確実にチップを回収すればいいのです。
一方で、相手全員が慎重でミスの少ないタイプの場合、下手に攻めてもこちらが損するリスクが高くなります。そんなときは、GTOベースの安定したプレイで相手の隙を待つ方が、結果としてうまくいくことが多いでしょう。
また、プレイヤー個々の力量やスタイルによっても違いがあります。たとえば相手の癖を読むのが得意で機転が利くプレイヤーは、多少危険を冒してでもエクスプロイトした方がトータルで稼げるでしょう。一方で「あまり相手のことは読めないけど、自分のセオリー通りにプレイするのは得意」という人は、無理に相手に合わせるよりGTO通りにプレイした方が結果的にミスが減り利益が出ます。
自分がエクスプロイトを使いこなせるレベルかどうかも関係してきます。実戦では「分かったつもり」で相手の傾向を判断して痛い目を見ることも多いので、確信が持てないうちは無理に奇をてらわない方が良い場合もあります。
さらに付け加えるなら、稼ぐ目的なのか上達目的なのかによっても答えは変わります。もし純粋に収支だけを追求するなら、自分が勝てるフィールドで徹底的にエクスプロイトしまくるのが手っ取り早いでしょう。
たとえば、初心者ばかりのテーブルでは、強いハンドでしっかりとバリューベットを繰り返すだけでも、大きな利益につながります。
しかしプレイヤーとしての成長を考えるなら、あえてGTOの練習をしてみたり、自分より上手い人とも戦ったりする中で長期的視野に立ったスキルアップを図ることも大切です。
短期的な稼ぎだけを見ると効率が悪く感じることも、長期的には高度な局面で活きてくる学びになるかもしれません。結局、「稼ぐ」という言葉の定義を目先の利益に置くのか将来的な自己投資に置くのかで、GTOとエクスプロイトのどちらに重きを置くべきかも変わってくるでしょう。
以上のように、「どちらが稼げるか」の答えはケースバイケースで、常にどちらかが正解というわけではありません。一言で結論付けるのは難しく、だからこそポーカー戦略の議論は面白いとも言えます。
それでは最後に、GTOとエクスプロイトのハイブリッドな使いこなしについて結論をまとめましょう。
まとめ:ポーカーでの最強の戦略は切り替え戦略
GTOとエクスプロイト、どちらも極めていけば強力ですが、最強なのは状況に応じて自在に二つを切り替えることです。
結局のところ、ポーカーは常に状況が変わるゲームです。たった一つの戦略だけで、あらゆる場面に対応するのは現実的ではありません。 どちらか一方だけでは不十分で、両方を理解し、場面ごとに上手く使い分けてこそ、本当に強いプレイができるようになります。
初心者のうちはエクスプロイト寄りで実戦経験を積み、勝つ感覚を養うのが近道です。【まず勝てる相手に確実に勝つ】という成功体験はモチベーションにも繋がります。そして並行してGTO理論の勉強も少しずつ進め、強い相手にも通用する土台作りをしておきましょう。
中級者になってくれば、基本戦略はGTOベースにシフトしつつ、ここぞという場面ではエクスプロイトにギアチェンジ…というように両者を融合させたプレイが理想です。上級者になればなるほど瞬時の判断でバランスを調整し、「自分は常にGTO 70:エクスプロイト30でいく」といった具合に自分なりの黄金比も見えてくるかもしれません。
重要なのは、両戦略は敵対するものではなくお互いを補完し合う関係だという理解です。GTOしか知らなければ相手の弱点を突けませんし、エクスプロイトしか知らなければ自分が弱点だらけになります。
GTO Wizardブログでも「どちらか一方だけを学んでも不十分で、両方を理解して初めて戦略の本質が見えてくる」と指摘しています。まさにその通りで、両方の視点を理解することで、どんな相手や状況にも対応できる柔軟な強さが身についていきます。
最後になりますが、読者であるあなた自身にとって最適なバランスは、プレイを重ねる中できっと見つかります。性格や得意分野によっても向き不向きがあるので、「自分は読みが鋭いからエクスプロイト多めでいこう」「自分は堅実派だからまずGTOをしっかり守ろう」など試行錯誤してみてください。
その上で、「ここは攻め時!」「いや我慢のしどころ…」と戦況に応じて戦略スイッチを切り替えられる柔軟さを身につければ、勝率はぐんと上がるはずです。 理論と実践、守りと攻めを自在に操る——それこそがポーカーにおける最強の戦略です。
GTOとエクスプロイトという2つの武器をバランスよく使いこなし、あなたなりの勝ち方を実戦の中で見つけてみてください。きっと今まで以上にポーカーが面白く感じられることでしょう。Good luck!🏆
(参考文献:Upswing Poker、GTO Wizardブログ、BlackRain79など)



コメント