GTO WizardやNTポーカーなどのGTO学習ツールを使い始め、チャート通りにプレイしているのにいっこうに勝てない…と悩んでいる人は多いのではないでしょうか。
よく聞くのは「GTOを覚えれば最強戦略だと思ったのに…」という疑問です。しかし実際には、GTO戦略とはあくまで理論上の「均衡」であり、完璧に再現することは人間にはほぼ不可能です。
そこで今回は、初心者・中級者がGTO学習でやりがちな誤解・間違いを5つに分けて解説します。
「チャートを完コピすれば勝てる」と思っている
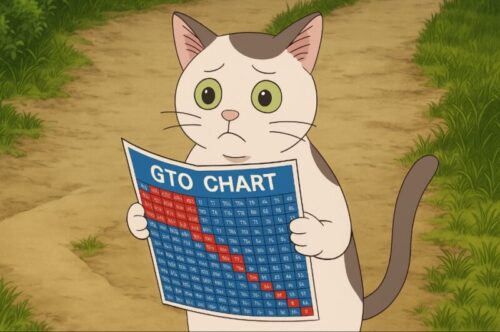
「ソルバーのチャートを丸暗記すればOK」と思い込むのは、よくある誤解の一つです。しかしGTO戦略は極めて複雑で、現実のゲームで完璧に再現することは事実上不可能です。GTOは数え切れないほど多くの状況を考慮し、各手札に最適なラインを示しますが、その膨大な情報量を人間が記憶してリアルタイムで適用するのは非現実的です。
ソルバー出力はあくまで「理想の基準」であり、弱いプレイヤー相手に完全にGTOで戦っても、むしろ稼ぎ損ねる可能性があります。したがって、「チャート通りに打てば勝てる」と期待するのはあまりに単純化しすぎており、実践では柔軟性が求められます。
いつも同じサイズ、同じアクションで固定してしまう

GTOソルバーは状況に応じて大小さまざまなベットサイズを使い分けますが、初心者はしばしば「とりあえずいつも3分の2ポットベットだけ使う」など、サイズやアクションを固定しがちです。これではバランスが取れず、相手に戦略を見抜かれてしまいます。
プロポーカープレイヤーのフィル・ガルフォンド氏は、理論上の最適戦略では「非常に多くのベットサイズを使い分ける必要がある場面もある」と指摘しています。実際、GTO戦略というのは、相手に対して“エクスプロイトされずバランスを取る”ために、状況に応じて細かくサイズを使い分ける設計になっています。
しかし人間が複数のベットサイズを実戦で正確に使い分けるのは思った以上に難しく、多くのプレイヤーは現実的に2〜3種類程度に絞ってプレイしています。
とはいえ、そこに甘えて毎回同じサイズや決まりきったアクションばかりを繰り返していると、プレイのパターンが固定化され、簡単に読まれてしまいます。実際には、GTO戦略ではボードや相手のタイプによってベットサイズを柔軟に変えることが前提となっており、常に最適なラインは一つではありません。
GTOを学ぶうえでは、「複数サイズを使うべき場面がある」ということを意識しつつ、自分が扱える範囲で少しずつ使えるベットサイズの幅を広げていくのが現実的で、かつ効果的なアプローチです。
頻度の考え方を誤解している(ベット or チェックの単純化)

GTOソルバーは、ある手札に対して「このボードでは33%の頻度でベット、67%でチェック」といった混合戦略(ミックスストラテジー)を示すことがあります。
ですが、初心者はこれを「強い手ならベット、弱い手ならチェック」というように、単純に分けて解釈してしまいがちです。
たとえば、GTO WizardではJ♥9♦のようなハンドが、あるボードでは「ときにはベットし、ときにはチェックする」という戦略が推奨されていることがあります。これはランダムにやっているわけではなく、相手に「ベット=強い」「チェック=弱い」と読まれないように、意図的に混ぜているんです。
もし、強い手は必ずベット、弱い手は必ずチェック、と毎回同じパターンで行動していると、相手からすぐにバレます。たとえば、「この人、ベットしてきたから絶対強いな」と思われた時点で、相手は簡単にフォールドしたり、戦略を変えて対応してくるでしょう。
GTOの本質は、相手がどんな行動をしても「これが正解だ」と簡単に決められない状況を作ることです。そのために、同じハンドでも頻度を分けて複数のアクションを取る=混合することが重要なのです。
頻度の数字だけを見て「何%ならベット」と表面的に理解するのではなく、「なぜ混ぜるのか?」「どうすれば読まれにくくなるのか?」という視点で考えることで、GTOの理解はグッと深まります。
相手がGTOじゃないのに、自分だけGTOで戦う

GTOはあくまで、ミスをしない上手なプレイヤーを前提とした戦略です。相手が弱点だらけのプレイヤーなら、「GTO通りにお互いバランスを取る」よりも、その弱点をついて攻めるほうが実際には儲けが大きくなります。
ポーカープロのPete Clark氏とMark Goone氏は「EVを最大化するには、相手のレンジを読み取ってエクスプロイトすることにある」と述べています。彼らはさらに、「テーブルにいる酔っ払った相手に対して『自分はバランスを取れているか?』ばかり考えてプレイするのはクレイジーだ」とも指摘しています。
また、「ライブでGTOを忠実に再現しようとしていたプレイヤーは、むしろ負けていた」という声もあります。
つまり相手がガチガチのGTO戦略で来るとは限りません。むしろ相手に対応した柔軟な読みや調整、エクスプロイトが実力アップには重要なのです。実戦では、相手の傾向に応じてGTOラインをずらし、より有利な方向に作戦を変えることも検討しましょう。
GTOだけ学べば上達すると思っている
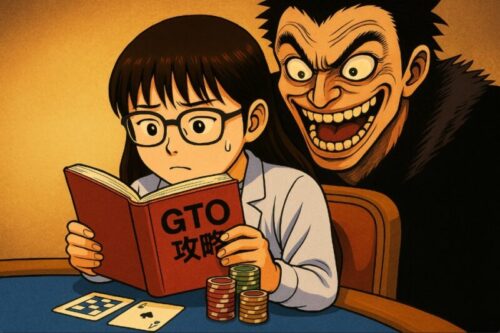
「GTOを学習すれば全て解決」という考え方も誤りです。確かにGTOを知ることは強力な基礎になりますが、ポーカーは相手との心理戦・駆け引きの要素も大きく、テーブルの雰囲気や相手の性格を無視するわけにはいきません。有名プロCharlie Carrel氏の「ポーカーは人対人のゲーム。GTOに固執しすぎず、相手の様子を見て判断しろ」と強調しています
ここで重要なのは「Carrel氏がGTO学習を否定しているわけではなく、あくまでGTOは全体の一部に過ぎない」という点です。実際、Carrel氏自身もハイステークスではバランスの取れた戦略を用いると語っており、GTOの重要性を認めています。「GTOを覚えれば最強」という考え方は「最善手を指し続ければプロに勝てる」と同じくらい非現実的です。
要するに、ソルバーチャートだけを覚える勉強法に固執せず、実際のプレイ経験や相手研究も組み合わせるのが上達の近道です。
まとめ:GTOは「基準」であって「最終目的」ではない

ここまで見てきたように、GTO学習には多くのメリットがありますが、「GTOを完璧に再現する」「GTOだけで勝つ」といった発想には注意が必要です。GTO戦略はゲーム理論上最もバランスの取れた戦略であり、それを知ることは「相手がどこでバランスを崩しているか」「どんな傾向があるか」を推し量る基準になります。
実力を伸ばすには、このGTO基準を踏まえた上で、相手に合わせて微調整する柔軟性が必要です。
逆にGTOばかりにこだわると、実戦での判断が硬直してしまいがちです。GTOを学ぶことは確かに近道ですが、それを唯一の目標とせず、相手や場面に合わせて攻略法を変えることが真の実力アップにつながります。



コメント